昨今、歯科医の得意領域である唇のアートメイク(リップアートメイク)が気になる方は多いのではないでしょうか?
リップアートメイクは唇全体に自然な血色を与えたり、輪郭を整えたり、くすみの補正ができたりと、口角の印象を調節することに効果的なアートメイクです。
今回はそんなリップアートメイクの特徴やデメリット、失敗しないコツなどをご紹介させてただきます。
⭕️ この記事でわかること
・リップアートメイクの特徴
・リップアートメイクの”もち”やダウンタイムについて
・リップアートメイクのよくある失敗・原因・対策
・リップアートメイクを歯科医で受けるメリット
・リップアートメイクに関して気になる方からのよくある質問と回答
リップアートメイクの特徴

リップアートメイクとは?
リップアートメイクは、表皮の浅い層に色素を薄く重ね、“素の血色”を底上げする施術です。
唇のアートメイクは口紅のツヤや質感を固定するものではなく、すっぴんでも顔色が良く見える唇のベースを作ります。
唇周りの輪郭や色のムラを補正するだけではなく色素も調節してくれるので、中期的にリップを塗るお化粧の手間が省けたり、自然な見た目で唇の印象を変えることができます。
タトゥーと比べて痛みが少ないアートメイクは、色味の持続時間が短いことで細かくデザインの調節が可能なところがメリットの一つです。
| リップアートメイクで出来ること |
|---|
| すっぴんでも唇の血色を良く見せることができる |
| 唇の色のくすみ、縦シワを目立たなくして印象アップ |
| にじみがちな唇外周の輪郭を自然に整える |
| 正面・笑顔・発音時の唇の動きを見て、左右差を調節できる |
| 唇のサイズや印象を調節できる |
| 肌色・髪色・歯の白さに合わせた唇の色相/明度/彩度をカスタムできる |
| 唇のベースの色を定着させるのでリップメイクが薄く・短く済む |
| 唇の色素が定着するため、マスクや飲み会で落ちにくい |
| 完全に定着するわけではないので、加齢やトレンドに合わせて細かくリタッチできる |
リップアートメイクの”もち”やダウンタイムはどれくらい?
リップアートメイクのダウンタイムは、腫れの場合当日〜48時間。乾燥・皮むけは3〜7日で落ち着くと言われており、色は最初濃く見え→1〜2週で20〜40%トーンダウンして馴染んで行くと言われています。
リップアートメイクのもちは完成後6〜18か月で徐々に薄くなるのが一般的で、9〜15か月に1回の微調整で“常にちょうど良い印象”を保ちやすいと言われています。
ダウンタム中はこまめにケアを行い、見た目の印象を自然に保てるように心がけましょう。
※効果には個人差があります
| リップアートメイク後の日数 | 体幹・見た目 | ケア方法・注意 |
|---|---|---|
| 0日目(当日) | うっすらとした腫れ・ピリつき。発色は想定より濃い | ・冷却、保湿(ワセリン等)を行いましょう。 ・熱い/辛い/酸っぱい/熱酒は控えて、うがいで唇の清潔を保ちましょう。 |
| 1–2日目 | 腫れのピークはこの期間に治りやすい | ・強い運動・サウナ・長風呂・摩擦は控えましょう。 |
| 3–5日目 | 乾燥や薄い皮むけ。色はまだ濃い〜やや暗めになる | ・無理に皮をめくらず保湿を継続し、紫外線を回避しましょう。 |
| 6–7日目 | 皮むけが落ち着き、色が淡く見える | ・唇中層の色が1〜2週かけて戻りつつ馴染む期間です。 色が淡くなっても焦らずにいましょう。 |
| 8–14日目 | トーンが安定し落ち着く | 一般的な化粧を施す場合は低刺激リップから始めて、クレンジングは優しく短時間で行うようにしましょう |
唇のアートメイクを失敗させないためのチェックリスト
唇のアートメイクによくある失敗と原因

唇のアートメイクでよくある失敗は、大きく分けて7つあります。
唇のアートメイクでよくある失敗の原因は、
✅ 唇のみのデザインを考えてしまうことによる不自然さやアフターケア不足といった「リップアートメイクを受ける側の原因」と、
✅ 施術のテクニックや石器絵・説明不足といった「施術側の原因」
といった2種類の原因に分けられます。
1、濃すぎ・不自然な色
2、輪郭が硬い(リップライナー感/いかつい口元)
3、左右差(厚み・口角ライン・山の高さ)
4、色ムラ・斑点(パッチー)
5、退色時の黄変/灰味
6、にじみ(色素のブリーディング)
7、想定外に早く薄くなる(“もち”が悪い)
唇アートメイク失敗の原因・予防・対策方法をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| リップアートメイク失敗時の症状 | リップアートメイク失敗の主な原因 | リップアートメイク失敗の予防/対処 |
|---|---|---|
| 色が濃すぎ・不自然 | ・一撃で色を濃く入れる ・肌、歯色と不整合 ・照明下の色評価ミス | ・薄層多層で“徐々に印象を安定させる”設計にする。 |
| 輪郭が硬い(縁取り感) | ・粘膜〜皮膚の移行部に強ライン ・グラデ不足 | ・最初からオーバーラインを強くしない。 ・硬い縁は周囲を薄く覆う補正で緩和する。 |
| 唇の印象に左右差がある | ・動的評価不足(正面だけで設計) ・下描きズレ ・腫脹見込み違い | ・正面+笑顔+発音時の“顔の動きがある状況下”でデザインを設計する。 ・下描き段階で複数角度の承認。 |
| 唇の色ムラ・斑点 | ・針圧、深度の不均一 ・乾燥、出血コントロール不足 ・術後の剥離 | ・出血・乾燥の管理、保湿を徹底する。 |
| 退色時の黄変/灰味 | ・色素選定ミス ・過度の日焼け、摩擦 ・濃く入れ過ぎ | ・高品質色素で補色設計を行う。 ・紫外線を避け、保湿を行う。 |
| 唇の色のにじみ(ブリーディング) | ・深打ち施術 ・血流が強い部位へ過量施術 ・術後摩擦 | ・浅い層に薄く施術する。 ・出血コントロール、初週の摩擦/サウナ/長風呂を控える。 |
| リップアートメイクのもちが悪い | ・薄すぎる(淡色選択) ・ホームケア不徹底 ・UV、摩擦が多い | ・初回は2回前提でリップアートメイクを行う。 ・紫外線を避け保湿を継続して行い、摩擦を回避する。 |
| 炎症・ヘルペス再燃・感染 | ・既往症状の未申告 ・無菌手技の不備 ・刺激強いケア | ・事前に炎症、ヘルペス等他にも体に症状がある場合は申告する。 ・症状出たら医療受診と治療を優先する。 |
リップアートメイクは「歯医者」で成功率と安全対策アップ!?
歯医者がリップアートメイクを行うメリット

歯科医が行うリップアートメイクのメリットは、安全性・痛み管理・デザインの一貫性(施術技術の高さ)です。
アートメイクは日本では医療行為に当たるので医師や看護師の資格保有者しか行うことができません。
そのため施術技術や知識に関して医学的治験を用いて対処が可能で、施術前後に安心してリップアートメイクを受けることができます。
| 歯医者がリップアートメイクを行うメリット | 詳細 |
|---|---|
| 痛み・出血・腫れのコントロールが的確 | ・口唇、口腔粘膜の解剖と血流に精通しており、局所麻酔や止血の適切運用で、施術中の苦痛とダウンタイムを最小化できる。 |
| 衛生管理・感染対策が医療水準 | ・滅菌器具、無菌操作、交差感染対策が標準化しており、炎症が起きて色ムラになるリスクを低減。 ・ヘルペス既往への予防内服指示が可能。 |
| “動的デザイン”の整合性が高い(笑顔・発音まで綺麗) | ・歯列、咬合わせ、口角の可動域、スマイルラインを踏まえた下描きができるため、 正面だけでなく笑顔、発音時も破綻しにくい輪郭に仕上がる可能性が高い。 |
| 歯の白さ・歯ぐき色との色彩調和が均一 | ・歯冠色(シェード)や歯肉の色相を参照して色を設計できるため、退色期でも“浮かない血色”になりやすい。 |
| 合併症リスクの事前評価と対応力 | ・既往歴(アレルギー・内服・皮膚疾患)に基づく適応判断が可能なため、禁止事項の見極めや中止判断が迅速に行える。 |
| “印象を育てる設計”で失敗を回避 | ・薄層多層+リップアートメイク2回仕上げを徹底。 にじみ・縁の硬さ・過度な濃色化を回避し、年1回の微調整で自然さを維持できる可能性が高い。 |
| 審美メニューとの連携で仕上がりを底上げできる | ・ホワイトニング、歯肉の色改善、口角ボトックス等とワンチーム設計で施術を行うため、唇だけ浮かない印象を作れる可能性が高い |
| 万一のトラブルへの医療対応 | ・炎症、アレルギー等が発生した場合の医療的介入ルートが明確で安心。 |
リップアートメイクを行う際の、歯科医と他職種との違い
| 観点 | 歯科医 | 一般の美容施術者 |
|---|---|---|
| 麻酔・止血 | 医療的に適正 | 制限があることが多い |
| 衛生管理 | 医療基準の滅菌・院内感染対策 | 施設により差 |
| デザイン | 歯列/咬合/スマイルラインまで考慮 | 静的デザイン中心になりがち |
| 色設計 | 歯色・歯肉色と統合 | 肌・髪ベース中心 |
| 合併症対応 | 医学的評価と処方が可能 | 医療連携が必要 |
| トータル審美 | 口腔審美と同時提案が可能 | 医師等の連携が必要 |
まとめ:唇のアートメイク(リップアートメイク)は歯医者がおすすめ
今回はリプアートメイクの特徴やデメリット、色変化について解説させていただきました。
リップアートメイクは施術前後に注意点があるものの、歯科医で施術を受けることによりトラブルの防止・対策において正確で安心して施術を受けることができます。
唇のアートメイクが気になっている方はまず近くの歯科医でリップアートメイクの相談をしてみましょう。


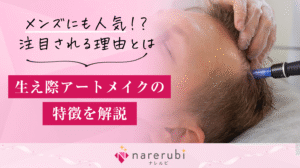




コメント